目次
だれがどれくらい受け取るのか
法定相続の場合、相続人それぞれが、どのような配分で相続するのでしょう。
遺言書を作成する場合にも、法定相続分を知っていると、円満な相続を実現することができます。大切な財産を、家族誰もが納得するように譲りたいものです。
だれにどのくらいの財産をのこせばいいの?
相続人は分かったけれど、誰にどのくらいの財産をのこせばいいのだろう。悩ましいところです。ご自身の亡きあと、残された家族みんなが納得し、仲良く暮らしてゆくことを、望まない人はいないと思います。
けれど、「この子にはこれくらいでいいのだろうか」「兄弟姉妹と不公平はないかな」などと不安もでてくるかと思います。
そんなときに、民法の定める法定相続分を知っていると、安心して遺言書の作成を進めることができます。
民法で決められた相続分
ここからは民法の基本である法定相続分のご説明をします。この基本を知っているだけで、遺言書を作成するとき、また遺産分割を進めてゆく時も、スムーズに進めることができます。
| 法定相続人 | 法定相続分の定め |
| 配偶者のみ | すべて |
| 配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
| 子のみ | この数で均等割り |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
安心して遺産をのこすために
民法900条に定めた法定相続分は、遺言により遺産相続を行う場合の基本となります。実際には、被相続人の生前に婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての生前贈与を受けていた場合や、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した相続人がいた場合、相続人の間での不公平をなくすための制度があります(民法903条:特別受益者の相続分、民法904条の2:寄与分)。
それぞれのかたの状況に応じて遺産分割の額を決め、遺言書を作成しておくと安心ですね。
当事務所では遺言書作成のサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。
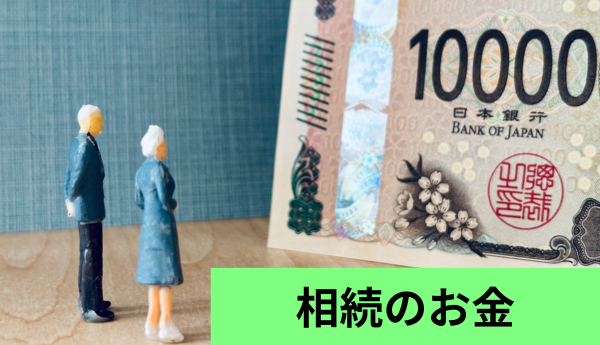
コメント